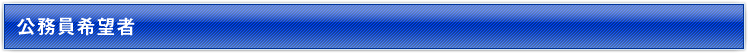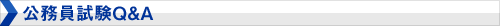





試験制度・業務内容・募集要件に関わる質問
「国家一般」というものが具体的に、どういう仕事なのかわかりません。
国家総合職・国家一般職試験については、試験区分であり登録試験ですから、最終合格をしてもイコール採用ではないのです。ここが、他の試験と異なる部分です。
この2つの試験区分は、1次試験(筆記試験)が合格した段階で、自分の希望する官庁に訪問をして採用してもらえるように話を進めていきます。簡単に言うと合格したら、あとは民間企業のように活動をするのです。
ちなみに、北海道で国家一般職に登録になると次のような官庁で働くことができます。
◎北海道管区行政評価局 ◎北海道総合通信局 ◎検察庁 ◎法務局 ◎地方更生保護委員会 ◎札幌出入国在留管理局 ◎北海道公安調査局 ◎函館税関 ◎北海道労働局 ◎北海道農政事務所 ◎北海道森林管理局 ◎北海道経済産業局 ◎北海道運輸局 ◎札幌管区気象台 ◎小樽検疫所 ◎北海道厚生局 ◎北海道開発局 ◎北海道防衛局 ◎陸上自衛隊北部方面総監部
など
これらの官庁については、採用されるとほとんどが北海道内での仕事になります。また、採用されると他の官庁に異動することもありません。たまに、東京の霞ヶ関の本省に出向ということもありますが、基本的には、北海道での勤務になります。
また、各官庁について詳しく知りたい場合は、人事院が主催する官庁説明会を覗いてみるのもいいと思います。
試験制度・業務内容・募集要件に関わる質問
年齢制限や職歴がハンディにはならないか?
年齢制限については、各公務員試験の応募要件が異なります。各試験の募集要項については、学内のキャリア情報室のファイルに綴ってありますので参考にしてください。
昨今は、公務員受験者の減少傾向を背景に応募条件の年齢を引き上げる自治体が増えてきています。また、新たに社会人枠を設ける自治体も増えてきています。
前職の有無についてもハンディになることはありません。むしろ、社会経験があるという強みを持って受験すべきです。
ただし、合否に関係はありませんが、「前職の事について」「どうして辞めたか」については、必ず聞かれますので説明できるように準備してください。
試験制度・業務内容・募集要件に関わる質問
公務員の実際の業務内容を詳しく知りたい。
3年生初夏のガイダンスでも紹介程度はする予定ですが、特に関心のあるものは自分でも調べてみてください。ここで詳しく説明するのは難しいので、調べる手段だけでも紹介しておきます。
- ホームページで先輩職員の体験談などを読む
- 採用パンフレットを読む
- 学内の官庁説明会に参加
- 学外の官庁主催の採用イベントに参加
- OBや知り合いのつてを使って職場訪問
- その官庁主催のインターンシップ・ボランティアに参加 など。
いずれにしても「合格するため」とか「面接で有利そう」という気持ちでなく、「そこで働いたら何ができるんだろう」という好奇心をもって臨むことが大事です。
試験制度・業務内容・募集要件に関わる質問
高卒対象と大卒対象では難易度はどう違いますか?
当然ですが、問題自体の難しさでいうと「高卒対象<大卒対象」です。
また、課される試験はやや異なり、高卒対象では英国数社理のような学科科目や漢字読み書き、時事的な一般教養なども課されたりします。
ちなみに高卒対象としているものは年齢・学歴によって受験ができない場合もありますので、募集要件をよく確認しておいてください。
試験制度・業務内容・募集要件に関わる質問
試験によって難易度にはかなりの差があるのでしょうか?
主要な試験の難易度をランク付けするとどうなりますか?
国家総合がダントツで難しく、札幌市〜国税はほぼ横並び、以下はやや平易です。公務員試験は受験者間で相対的に評価されますので、あくまで参考にしてください。
試験制度・業務内容・募集要件に関わる質問
警察の視力検査・身体検査で引っかからないかが不安です。
視力検査に限らず身長・体重などの要件が微妙に足りない、という程度であれば受験した方がいいでしょう。
これらの基準は一般に「おおむね」などのあいまいな表現で書かれています。つまり警察官としての資質が十分であれば、多少基準に満たない部分があっても不問となります。
この許容範囲は採用先により異なるので、不安な場合は官庁説明会のときなどに採用担当者へ相談してみてください。
試験制度・業務内容・募集要件に関わる質問
司書・学芸員の資格を活かすにはどこを受験したらいいですか?
司書・学芸員・社会教育主事は自治体・学校等の教育機関や研究機関が、一般の行政職とは別に独自で募集をかけるケースが多いです。
ただし、雇用の形態としては期間契約やアルバイトなどが多く、正職員としての採用を毎年おこなっているわけではありません。したがって、正職員をめざすのであれば道内にこだわらず全国に目を向け、求人がなかったときでも行政職として知識を活かしてできることはないか考えておくと良いでしょう。
また、行政職として入職しても、所有している資格を活かせる配属をする場合も多くあります。
なお、司書等の有資格者限定の採用情報をキャリア支援センターで入手した場合、教務センターへ情報提供し、担当教員から資格取得者へ周知します。
勉強方法・筆記試験に関わる質問
勉強時間はどれくらいとったらよいか?
よくある質問ですが、難しい質問です。どれくらいやれば受かるという指標は、合格している人でもなかなかわからないものです。むしろ、自分で経験をして1つでも受かったという自信から指標が生まれてくるものだと思います。
しかしながら、それでは回答にならないので、過去のデータで答えます。毎年3年生の3月(受験直前期)にアンケートをとっています。6時間以上と答えている学生が、割合的には一番多いです。
結果をみても、安定的に6時間以上の勉強を続けている学生の合格率は非常に高くなっています。実は、この受験直前期は公務員講座も過密なスケジュールになっていますし、模擬試験の復習にも追われる時期です。
それぞれの学習の仕方にもよりますが、受かっている学生ほど、最後は勉強時間が足りないと言います。どれくらいという質問の答えには少々曖昧かもしれませんが、学習計画を立ててみてから判断してはいかがでしょうか。
学習計画についての相談はキャリア支援センターで行っています。
勉強方法・筆記試験に関わる質問
教養・専門・2次に対する勉強時間の配分は?
教養・専門の配分について考える場合は、まず次のことを考えてください。
- ①志望度の高い受験先が国家公務員なのか、地方公務員なのか。
- ②どちらが不得意か。
- ③自分の受験科目に専門があるかないか。
③については、当然考えることだと思いますが、問題は①です。国家公務員には、傾斜配点が掛かっているものがあり、専門の得点が高いと全体的に有利に作用するものがあります。国家総合職・一般職・国税専門官等がそれにあたります。
一方、地方公務員は、ほとんどが教養・専門がフラットで判定されます。しかし、大切なことは②の部分です。自分の実力で今、何が不足しているのかということを考えて欲しいと思います。
一般的なことをいうと、専門試験は難しいイメージを持っている人が多いのですが、最終的に安定した点数が取れるのは、専門試験の方です。
教養試験は、一般知能分野は問題演習を重ねていくことで得点は安定しますが、一般知識分野はそれこそ範囲が膨大ですので点数をまとめることは至難の業です。一般知能や専門を捨てて、一般知識で勝負するというのは、負け戦になると思います。
勉強方法・筆記試験に関わる質問
1問をどのくらいの速さで解答できると合格ラインに乗れるのかが気になります。
出題数と解答時間で計算すると1問3〜4分となりますが、得意な問題はより早く、捨て問は0分とみれば時間をかけてもいい問題も出てきます。大事なのは「解ける問題を探して解く時間(+適当にわからないところを埋める時間)」を確保して、確実な得点源を積み重ねられるかです。
「より早く」と意識するのは良いですが、あまり具体的に何分とは考えず、「多少時間をかけてでも確実に解ける問題を増やす」ことを優先してください。
最終的には模擬試験で全体のペース配分を考えながら、問題ごとにかける時間や感覚をつかんでほしいと思います。
面接試験に関わる質問
3年生の時期はどんな気持ちで過ごし、何をやっていたか?
【合格体験談より】
勉強面では憲法や一般知能に手をつけた頃でしたが、官庁説明会に行って業務について知り、自分はやっぱり公務員になりたいという気持ちを固めた頃でもありました。
それまでは、業務についても民間と公務員の違いについてもよくわからなくて、どちらにするか迷っていました。私はこの頃気持ちを固めたことで真剣に勉強を始めることができたと思っています。
まだ民間と迷っている人はどうして公務員になりたいか、説明会やHPなどを使って考えてみることもいいと思います。
勉強は長く、辛い時もあるので、なりたいという気持ちが弱いと大変だと私は思います。これについて考えて気持ちを固めると、勉強のモチベーションも上がるし、面接のときにも役立つのではないかと思います。
面接試験に関わる質問
面接で聞かれること/圧迫面接とは?
実際に質問されたことは、ミナトコムにアップしてある合格者の試験結果報告を参照してください。
また、圧迫面接は怖がらないでください。公務員になれば、当然いろんな人と接します。感情的になった人と接するときにどのような反応をするかを見ているのです。よく突っ込んだ質問があったらどうしようという相談もありますが、基本的に嘘をつかないで、落ち着いて対応しましょう。
面接試験に関わる質問
面接のイメージはわかりますが、実践するとなると不安です。
面接のイメージについては誤解の多いところですが、面接とは「会話を通じて、自分のことを一生懸命伝えようとし、相手に伝えられるかどうか」です。「相手の質問に無難に答えて、ミスがなければOK」ではありません。
つまり「伝えるべき自分の姿を明確に把握」「それを相手に納得してもらえるだけの材料を用意(エピソードや業種研究から)」「そういったことを相手に表情豊かに伝える」といったことがポイントになります。
小難しく書きましたが、要は「目上の方への色々な角度からの自己紹介」です。あまり肩肘をはって考えすぎないで欲しいと思います。
面接試験に関わる質問
面接対策でやっておくことはありますか?
おすすめは官庁説明会などのイベントに参加して、就職後のイメージを作ることです。公務員になったら関わってみたい業務や、「こんなまちづくりがしたい」など、待遇以外の魅力や将来の自分の姿をイメージしてみてください。勉強へのモチベーションにもつながります。
あとは自己分析も必要にはなってきますが、直前から始めても間に合わないということはありません(忙しくはなりますが)。まず筆記試験を通過しなければ話になりませんので、勉強を中心に考え、集中して取り組んでください。
面接以外の2次対策
論文対策はいつごろから始めたらいいですか?
論文試験のハードルは高くはありません。規定の文章量、誤字脱字が少ない、序論・本論・結論の流れがとれている、で十分合格圏です。内容もよほど幼稚な内容・批判的な内容でないかぎりは、すばらしいものを作らなくても結構です。したがって、早い時期からの準備は特に必要ありませんし、直前に作法を確認する程度で問題ありません(先輩も「論文対策をしっかりやっておけば…」という人はまずいません)。
教養論文では「自己PRや志望動機(公務員としての目標・官庁の業務理解など)」、専門論文では「過去問を通して科目の基礎知識を固める」ということができていないと、一度論文を書いてみるにしてもネタが出ませんので、これらの目処を先につけましょう。
その他公務員を目指すにあたっての質問
民間との併願が難しいと聞きましたが、公務員試験一本だと落ちた時が心配です。
確かにそういった不安はもっともで、周りの人からも併願を勧められている方は多いかと思います。しかし、合格や内定に結びつく確率は圧倒的にどちらか専願の学生が高いです。公務員志望者は、“集中して”勉強に取り組む時間をできるだけ多く確保したいところです。
そして民間企業も「なんとなく受けたら受かった」という人はごく少数で、内定を得るためにはしかるべき準備を一社一社入念にすることが最低条件になってきます。したがって両方に手をつけていくと、忙しくなるばかりで合格・内定への最低ラインを超えることが非常に困難となってきます。
最悪、公務員試験が全滅した場合に取れるルートは基本的に2通りです。
1つ目は「公務員試験にこだわり次年度再受験」。公務員試験では既卒者は現役生と同様に扱われます。民間と異なり、年齢制限の範囲にいる限り何年でも受験しなおせます。もう一年勉強というのは精神的にきついですが、この一年の経験は現役生に対し大きなアドバンテージになります。
2つ目は「民間企業へ進路変更」です。公務員試験が落ち着く8月以降でも継続して求人はあります。むしろ公益的な事業の企業はあえて秋以降に募集することも多いです。夏〜冬にも学内での合同説明会をおこないます。ただし活動をする場合は、民間志望へきちんと気持ちを切り替えて挑んでください。「とりあえず民間に入って、そこから公務員を目指す」という思いで挑んでも見透かされ、なかなか内定には結びつかないでしょう。「公務員を目指しながら収入を確保したい」のであれば、契約社員やアルバイトも視野に入れると勉強する時間は確保しやすいかと思います(ただし、そこの環境に甘んじてしまわないように注意!)。
その他公務員を目指すにあたっての質問
試験に受かっても卒業できなかった場合にはどうなりますか?
基本的に、年度をまたぐと合格したことが無効になるため、次年度に一から再受験しなければなりません。「働きながら大学に通いたい」と思っても、「大卒区分」として受験している場合は、採用基準に満たなくなるため対象から外れますし、その他の場合でも勤務地や職種によっては通えないため、「辞退するか退学するか」という決断をせまられるケースが多くあり、あまり期待はできないでしょう。
万が一、留年してしまった場合には、まずは正直に採用担当者に相談してください。また、こうならないように単位は計画的に修得しておいてください。
その他公務員を目指すにあたっての質問
模擬試験はどうすれば受験できますか?
12月中に学内模試・学外模試それぞれの日程を発表する予定です。申し込み方法は学内模試は大学生協で受付、学外模試も大半は大学生協で受付可能です。学内模試の実施日は2月上旬から毎週土曜日を予定しています。
なお、学内模試は学内公務員講座の受講生(3年)に限りすべて無料で受験できます。また、1・2年生や学内公務員講座を受講していない3年生、卒業生も有料にはなりますが、受験は可能です。模試の受験と復習は、最も実戦的かつ最も効果の高い学習になりますので、志望先にこだわりすぎず、色々なタイプの模試を受けてみてください。
|